
銘仙と紬はどんな違いがあるの?見分け方ってあるのかな。
銘仙も紬も肌触りが似ていて、見分けがつかないことありますよね。
そこで銘仙の歴史を追いながら、間違いやすい「紬」や「お召し」と比較してみました。
銘仙のように同じ絹織物でも、糸や織り方の違いで見分けられます。
銘仙の歴史を知ることで、他の絹織物との違いが明確になることでしょう♪
また銘仙のことがわかると、大正ロマンのお洒落を真似したくなるかもしれませんよ。
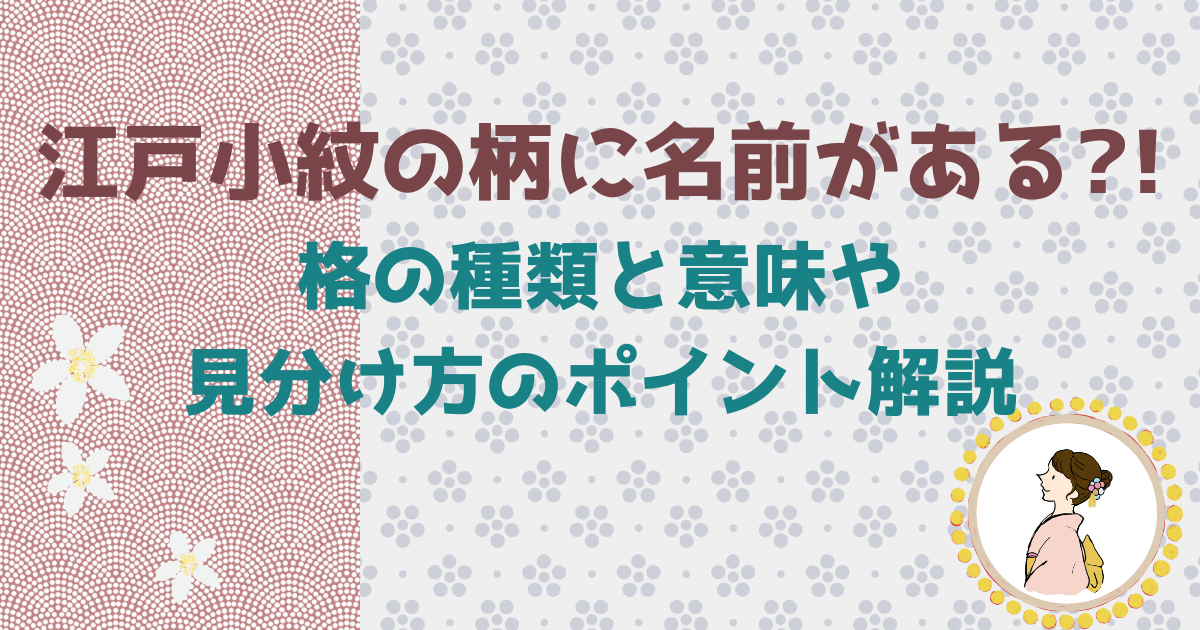
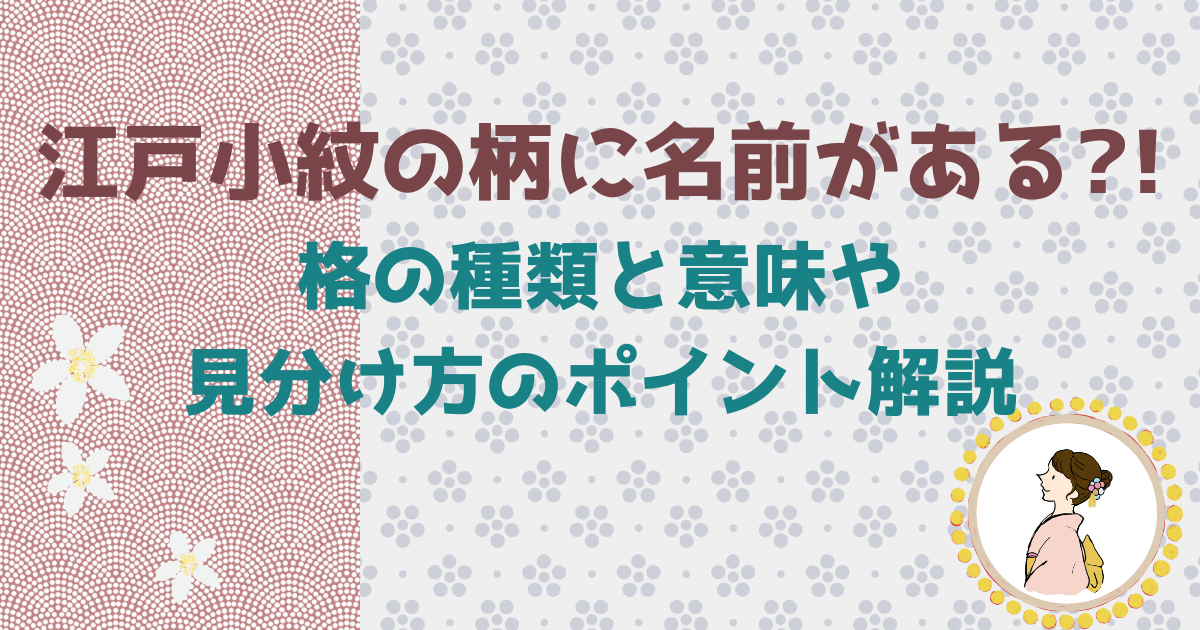
銘仙の見分け方は織り糸による質感の違いと時代の背景


銘仙着物は、織る前の糸を染めて柄を出す「絣(かすり)」という技法で織られた絹織物の着物です。
銘仙は「アンティーク着物」と呼ばれていて、普段着用でアレンジもできお洒落に着こなす着物として人気がありますよ。
織る前に糸を染め、意図的に経衣(たていと)と経糸(よこいと)をずらして織る「絣」という技法をつかうことで、色の境界がぼやけ通常の平織りでは見られないにじんだ柄になる
着物の中でも、カジュアルに着こなせることから大正から昭和にかけてお洒落着として日本中で流行しましたようですね。
銘仙着物が流行したのは明治・大正時代


銘仙は江戸後期がはじまりとされ、着心地と安さで明治・大正・昭和と庶民に広まりました。
はじまりは、養蚕(ようさん)農家の織子(おりこ)がくず糸を使って織ったのが銘仙と言われています。
当時の学校の制服に絵柄が少ない質素な銘仙に決まりましたが、女生徒には不人気だったようです。
しかし、明治中期に群馬の「伊勢崎ほぐし絣」という手法で鮮明な柄の銘仙着物が誕生し、人気を集めたことで需要が高まっていきます。
その後、各地で「ほぐし絣」の手法で銘仙を仕立て、大正から昭和にかけて全国的に普段着として最盛期を迎えました。
全国に広まりますが、ここで東と関西で色使いやデザインの違いが出ていますよ。
| 項目 | 関東(秩父・足利・伊勢崎など) | 関西(京都・滋賀など) |
| 柄の特徴 | モダン、幾何学模様、抽象柄など | 古典的、写実的な柄、和文様など |
| 色使いの傾向 | 赤、青、紫など強い配色 | ベージュ、茶、藍など落ち着いた配色 |
| モチーフ例 | チェック、縞(しま)、花柄、レトロ調の意匠(いしょう) | 桜、菊、松竹梅、亀甲文様、雲などの伝統文様 |
| 文化背景 | 大衆的で先進的なデザインが人気 | 品のある古典文様は四季の花を好む |
同じ地方によっても「絣」の手法は産地ごとに違うので、色のにじみ方でどの産地の銘仙なのかがわかりますよ。



銘仙の柄でも東と関西で好みの違いが出るなんて面白い♪
くず糸から織られた銘仙
銘仙は、玉糸(たまいと)と呼ばれる生糸で織られているため独特な風合いや質感があります。
繭(まゆ)が、2匹の蚕(かいこ)によって一緒に作られた玉繭からできる糸のこと
蚕は1匹で1個の繭を作ると、まっすぐなキレイは生糸ができます。
しかし、2匹以上の蚕が1個の繭を作ると糸が絡み合ってしまい、太さにムラができて節(ふし)のある生糸ができます。
このムラのある糸で織ることで、銘仙の独特な風合いが生まれるのです。
また、ムラのある生糸は高級な着物には使えないため安価であり、また撚り(より)をかけたり染めたりと加工にも向いていたことで銘仙は庶民の着物に適していました。



わざとムラを作るんじゃなくて自然に出来たムラで風合いが生まれてるんだ~
紬やお召しとの見分け方
紬(つむぎ)やお召し(おめし)も、先に糸を染めてから織られる着物ですが、織り糸の違いで見た目や肌触りが違います。
銘仙・紬・お召しは絹織物になりますが、絹糸の種類や織り方に違いがありますので、簡単に説明しますね。
| 種類 | 糸の種類 | 織りの特徴 | 格・用途 | 主な産地 |
| 銘仙 | 生糸に近い絹糸 節糸 | 絣模様などの大胆な柄が多 | 普段着・おしゃれ着 | 伊勢崎銘仙(群馬県)、足利銘仙(栃木県) |
| 紬 | 蚕の繭を手で紡いだ紬糸 | 節のある素朴な風合い | カジュアルな普段着 | 大島紬(奄美大島)、結城紬(茨城県) |
| お召し | 強く撚った絹糸 | シボと呼ばれる細かいシワ感があり上品 | セミフォーマル、おしゃれ着 | 西陣(京都) |
紬は、紬糸を使うことで節ができ、織って生地になる際に凹凸ができるので、光沢は控えめで素朴な風合いがあります。
丁寧につくられた紬は、三代着られるほど丈夫でとても貴重な着物になります。
お召しは、生糸を使っているため凹凸がなく光沢も続き高級感がありますよ。
そのため、お召しは織りの着物の中では最も格が高く、帯の合わせ方でセミフォーマルでも着用できます。



銘仙も紬もお召しも織りの着物になるんだね!
銘仙の代表的な産地5ヶ所の特徴をそれぞれ紹介!


産地:1 足利銘仙(栃木県)
足利銘仙は、栃木県北部の足利市近郊で、足利産の絹で織り上げます。
もともと織り物の産地として有名だったため、大量生産が可能だったため安価で製造販売ができました。
また、デザイナーや染め職人による高いデザイン性と、画家や大女優を起用したマーケティング力で足利銘仙の宣伝に成功したことで生産高日本一となりました。
質感…上品な光沢感と軽くてしなやか、普段着でも高級感がある
技法…型染めして緯糸を一度ほぐし「ほぐし織り」技法
柄…輪郭(りんかく)に、ぼかし・にじみが出て柔らかい印象
色彩…ビビッとな原色系、コントラストの強い配色
歴史…明治時代後半から大正・昭和初期にかけて一大産地になる
産地:2 桐生銘仙(群馬県)
桐生銘仙は、群馬県桐生市近郊で作られ、他の生産地と比べると生産量が少ないがクオリティが高いです。
お召し織りに使われる撚り糸で、お召しと銘仙の両方を兼ねそなえた生地が「西の西陣、東の桐生」と称されています。
織り…錦糸を先染めしてから織る先染め平織り
品質…お召し用途の糸を使い、強度があり光沢の美しい生地で別名「お召し銘仙」と呼ばれる
柄…小柄で細かい絣文様を細かいところも丁寧に表現している
生産量…他の産地に比べ生産量は少なめ、高級感と希少性がある
1977年(昭和52年)には、「桐生織り」として国の伝統工芸品に指定され、少ない生産量にもかかわらず高品質が保証されています。
産地:3 伊勢崎銘仙(群馬県)
伊勢崎銘仙は群馬県伊勢崎市を中心に作られ、足利銘仙と共に業界をリードしていました。
伊勢崎名産は併用絣(へいようがすり)と呼ばれる手法で織っているため、鮮やかで大胆かつ多様な柄の表現を可能にしています。
技法…たて糸とよこ糸を型紙で染めた絣糸を作り、柄ピッタリ合わせて織る技法
柄…幾何学柄、花鳥風月、動物モチーフなど、20色以上の色を使って鮮やかで抽象的なデザイン
品質…平織りで透け感もある軽さ、肌さわりも魅力
現代の評価…戦後は生産が激減、現代は市や有志、若手デザイナーによる復興プロジョクトが盛ん
作品の中には20色以上の色を使った着物もあり、ほとんどが手作業で伝統工芸品にも指定されています。
産地:4 秩父銘仙(埼玉県)
秩父銘仙は、ほぐし捺染(なっせん)と呼ばれる手法で裏表同じように染色されている銘仙着物です。
ほぐし捺染は、秩父出身の坂本宗太郎氏が編みだし明治41年に特許を取得しています。
技法…糸を先に染めてから織る「先染め」で、模様をプリントする前に一度織って模様をつけ、再
びほどいてから本織りする「ほぐし織り」
柄…幾何学模様や抽象的なデザインが多く、レトロポップな印象
質感…玉虫色の光沢があり鮮やかで、なめらかな質感
秩父銘仙は、国から認められた独自技法によって普段使いしやすいデザインを多いのも特徴の一つです。
産地:5 八王子銘仙(東京都)
八王子銘仙は、現在製造されていませんが、かつて八王子で作られていた銘仙をいいます。
最大の特徴は「カピタン織」と呼ばれる技法でドビー織とも呼ばれています。
経糸(たていと)の染糸を、緯糸(よこいと)に白糸を織り込む技法
カピタン織によってできる凹凸のある地紋が八王子銘仙の風合いを持っています。
現在では、ネクタイや小物などでこの技法は継承されています。
技法…秩父銘仙と同じ「ほぐし織り」。カピタン織りによる地紋が特徴
柄…上品で落ち着いたデザイン。幾何学模様やモダンな花柄が好まれた。
品質…養蚕(ようさん)と絹織物の中心地。上質な絹糸で作られ品質の高さ
流通の利点…都市圏の需要を意識し、最新の流行を取り入れやすかった
銘仙着物を着たい!着るタイミングはいつ?


銘仙は、街着やおしゃれ着なので普段着扱いでカジュアルなシーンで着られます。
着物の格としては、高くないので結婚式や式典などのフォーマルなシーンには着て行けませんよ。
銘仙を着る際のポイントとしては、季節にあった柄を選びましょう。
ですが、お洒落着なのでコーディネートの幅は洋服と同じです。フォーマル着物とは違ったコーディネートをたくさん楽しみましょう♪
まとめ


庶民の着物として広まった銘仙着物は、地域によって好まれた柄や織りがあるため、見分けるのは難しいかもしれませんね。
それでも銘仙着物は、大正ロマンの代表的な着物です。
洋風アイテムを合わせられるのも魅力の一つですよ。
是非あなた好みの銘仙着物を見つけて、いろいろなコーディネートを試してみてくださいね♪

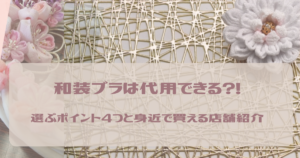

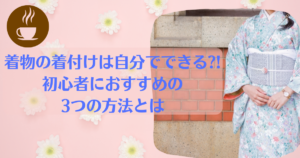

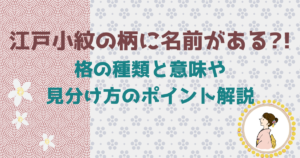
コメント